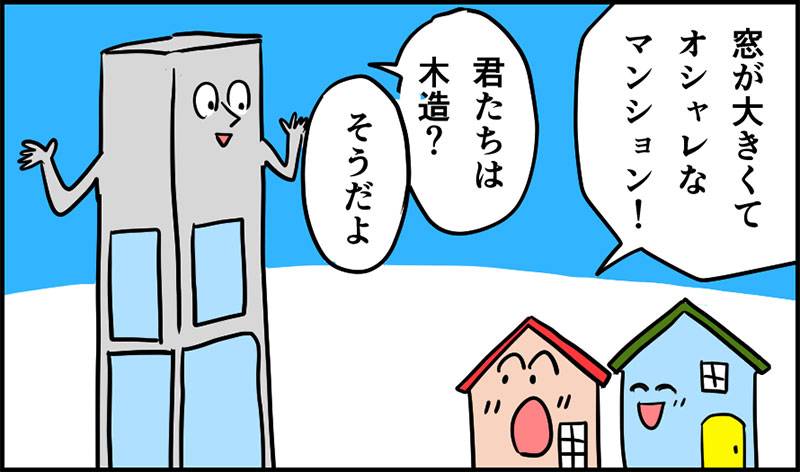高齢者住宅難民問題待ったなし

2020/01/27

2019年に噴出した“年金2000万円問題”。しかし老後の不安はなにも年金問題だけではない。老後の住まいが見つからない“漂流老人”がここ数年で急増し、社会問題になる可能性があるのだ。もしあなたが老後、住む家をみつけられなかったとしたら・・・。 『老後に住める家がない!』 を上梓した司法書士の太田垣章子氏に高齢者の住宅問題について聞いた。
――太田垣さんは、高齢者の住む家がなくなる住宅難民がここ数年で表面化していくと警笛を鳴らしています。
単身高齢者世帯は、2015年には601万世帯であったのに対し、2035年には762万世帯まで増加すると予測されています。日本はこの20年足らずで超高齢社会となりました。準備に時間がないのは分かりますが、このようにいびつな人口の偏りでは安心して子どもを産める社会とはいえません。子どもが苦労するのが当たり前の世の中で、誰が子ども産みたいと思うのでしょうか。制度、そして社会は完全に破綻しています。
私が司法書士として賃貸住宅のトラブルに携わったのは2002年からで、その頃は家賃滞納などの問題はありましたが、高齢者の住居問題はとくにありませんでした。その年代の人は、持ち家に住んでいたり、家族がなんとかしていたので、賃貸でのトラブルというもの自体がなかったのです。最近では高齢であるが故に住む家がない、立ち退き後に住む家が見つからないなどといった問題が顕在化しています。実際に私が担当している2~3割は高齢者の案件です。将来の不安を反映してかリースバック(所有していた不動産を売却した後、購入した第三者より当該物件を借り受けること)の登記なども増えてきました。巷では、「持家VS賃貸」などと言っていますが、そんな悠長な局面ではないことに全員が気付くべきです。日本は色々な面で対応が遅く、古い借地借家法に縛られていますが、現在の賃貸業界に果たして合っているのでしょうか? 誰も得していない。家主も借主も古い法律に苦しめられているのです。誰かが声を上げて、この問題を表に出さなければいけないと思ったのです。
――高齢入居者の受け入れを緩和させる制度として終身建物賃貸借契約(借主が死亡したときに契約が終了する賃貸借契約。通常の賃貸借契約では借主が死亡しても契約は相続人に引き継がれる)や住宅セーフティネットなどもあります。
終身建物賃貸借契約はほとんど使われていないという現状があります。ただでさえ、高齢者の入居は家主にとってハードルが高いのに、終身建物賃貸借契約は認可を受けなくてはいけない。当然届出も必要で、このことがさらにハードルを上げている。これじゃ誰も使わないですよね。住宅セーフティネットも同様です。本来であれば、国が高齢者のために住宅を用意しなければいけないはずなのに、できていないから民間の家主へしわ寄せがきている。なのに、国が決める制度には配慮がないのです。上から目線ではダメで、もっと現場の声を拾っていかないといけません。
――高齢者の住まいを考えるうえで家主と不動産会社のあいだに意識の乖離があるのも現実問題としてあります。
(不動産)管理会社からすると高齢者は遠慮したい、家主からすると家賃が入るのなら入居を受け入れたいという意識の差があるのは事実です。ただ、家主は入居後のトラブルを明確に想像できていない可能性もあります。管理会社は常に現場で対応しているため孤独死などを含め高齢者の居住対応の困難さを理解しています。些細なことかもしれませんが、「電気がつかない」「テレビがつかない」「リモコンがない」など、若い人であればなんてことはないことでも高齢者にはできないというケースもある。家主は、「管理会社が責任持ってくれるなら入居を受け入れる」というのではなく、みずから現状を把握し責任を持つことで(管理会社と一緒に)高齢者を受け入れる環境を作り上げることが必要となってきます。
――解決策を見出すのは難しい。
確かに解決策を見出すのはすごく難しいです。だからこそ、そこに関わる人たちの意識のあり方がまさに問われているのです。昨今感じるのが、家主業が不動産投資に変わってきているということ。昔の家主は入居者との繋がりがもっとあった。しかしながら現状の家主業は、不動産投資というお金の部分だけにフォーカスし、あとは管理会社に丸投げ。入居者を知らない家主が多くなっているのが現状です。家主は入居者に生活の場を提供している自覚をもっと持つべきではないでしょうか。
――それぞれの立場で意識を変えていかないといけないですね。
管理業務はどんどんアウトソーシングされてきています。家賃保証は保証会社、24時間駆け付けサービスなどのコールセンター、そして重要事項説明もIT化されてきています。自動化やアウトソースできるところは外部に任せて、逆に人にしかできない部分に注力する。すなわちそれは入居者とのコミュニケーションです。何もこれは賃貸業界だけのことではありません。例えば飲食店でロボットが、味が一定のご飯を作るとします。それを運ぶのがロボットでは味気ないですが、人が「お待たせしました」と笑顔で運べばあたたかさがありますよね。
いずれにしても家主としてラクして稼げるというのはこれからの時代では難しいでしょう。生活の場を提供するのであれば、入居者の生活に関わることを知っておく必要があるからです。国が行っている現状の仕組みでは、高齢者には貸したくないと思う家主がいるのもある意味仕方がないとも思います。そのなかで、貸す側も借りる側も自立し、現場の声を上げていく。そしてその声を拾って国も変わらなくてはいけない。
――自分の身は自分で守るという意識を持たなければなりませんね。
そうです。日本人にはもっと自立が必要。誰かがなんとかしてくれる時代は終わったのです。住宅は生きる基盤であり、必要不可欠なもの。今までの高齢者は家族に養われ、年金をお小遣いとして生活することができました。これからは子どもを頼れない時代になるのです。日本人は死ぬときの話は縁起がよくないと忌避しますが、死ぬときのことを考えるのは今を生きるために必要なことです。60代のうちに自身の70~80代を考え、これから先の人生をイメージしながら人生の棚卸をする。そして「子どもにどうにかしてもらう」というのではなく、きちんと自立し、自分の将来は自分で決めていくということが大切なのです。

『老後に住める家がない!』太田垣章子 著 ポプラ新書 刊 定価 880円(本体価格)+税
この記事を書いた人
賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン『ウチコミ!タイムズ』では住まいに関する素朴な疑問点や問題点、賃貸経営お役立ち情報や不動産市況、業界情報などを発信。さらには土地や空間にまつわるアカデミックなコンテンツも。また、エンタメ、カルチャー、グルメ、ライフスタイル情報も紹介していきます。